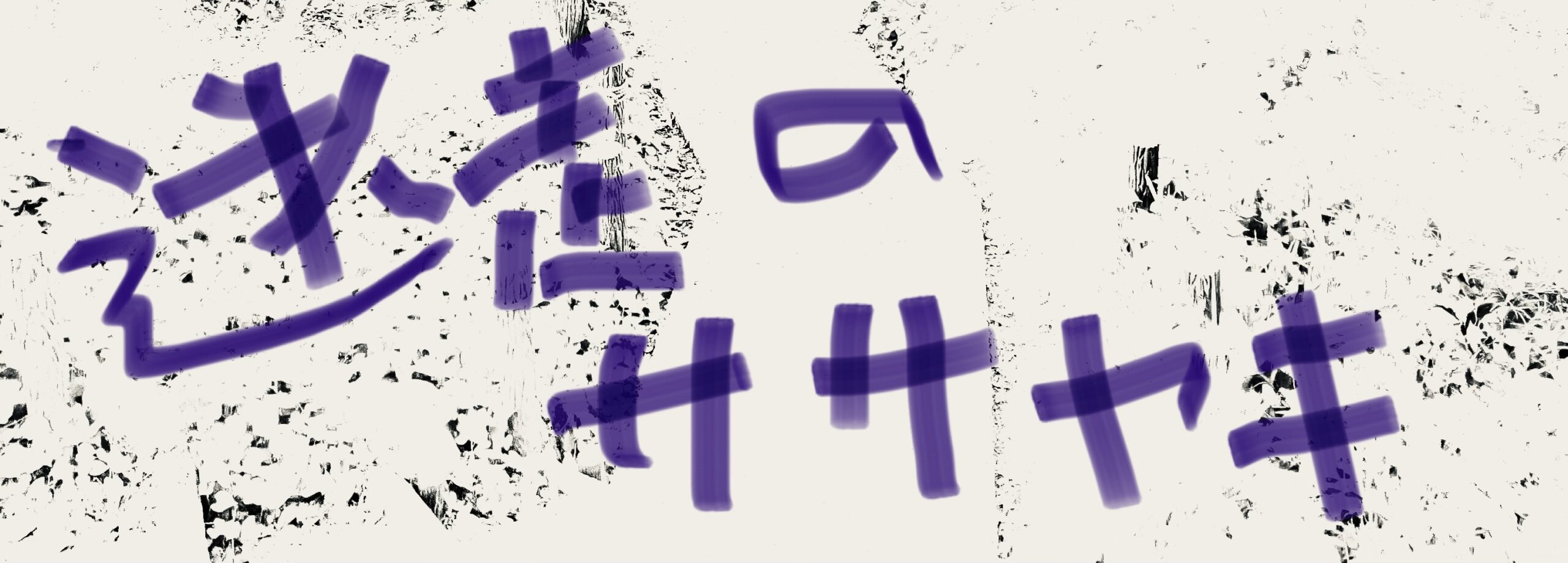「古代ギリシャ人は無からは何も生み出せないと考えていた」と、西洋古典語の先生は言った。無から何かを生み出せるという考えはキリスト教のものだとも。前者は論理的、合理的で、後者はその反対だ。
仕事柄、企業のなかで新規事業の創出に取り組む人に会うことがある。既存事業部と紐づいていない、コーポレート的な事業開発は、知見が社内にないこともあり、さながら無から有を生み出す営みだなあと感じていた。そんなわけだから、冒頭の先生の言葉を聞いた私は、悲しさを覚え、そして、そう先生に言った。
そうしたら先生は、「人間は不合理なものが好きだから」と言った。人間は完全に合理的であることもできない、とも。だからキリスト教は人気が出た。大体、そのような意の話だった。
無の定義をちょっと考えれば、少なくとも物質的には、無からは、何も生まれないと分かる。元になる材料が、何もないからである。完全無欠の無は、文字通り、何もないのだ。有機物も、酸素も、何もかも。そこから何かが生まれると考えることは、論理的に破綻している。
私がその真理を聞いて悲しさを覚えたのは、上述の企業で働く人の身の上を思ったからだけではない。そもそも、新規事業開発に取り組む人がいる状況が、まったくの無であることはあり得ない。開発用の資金があるだろうし、そこで働く人自身も一種のリソース、つまり何かを生み出す原料である。
それでも、無から有を生み出す、ゼロイチ的なイメージが新規事業開発につきまとうのは、なぜなのだろうか。そこには、そうあって欲しいという、願望のようなものがあるのではないか。
なぜかはわからないが、無から有を生み出すことが可能だと信じたい気持ちがあって、その気持は、考えている以上に支配的のような気がしてきた。だからこそ、私はそれが否定されたとき、悲しさを覚えたのではなかったか。
芸術家を、無から有を生み出す存在だと思う人は、多いのではないだろうか。しかし、絵の具やキャンバスといった道具があること以外に、何を描くかについても、有形であれ無形であれ、対象物が「有る」し、過去の画家たちが描いてきた絵が比較対象としても「有る」。つまり、描くための道具は置いておいたとしても、完全な無であることは、あり得ない。そう、そもそも、無という存在自体、概念的なもので、実際には、あり得ないのではないか。
本当は、もっと論理的にこのテーマを展開したいと思うのだが、そこまでの論理的思考力が私にはない。ただ、感情的に、無からは何も生まれないという言葉を聞いて悲しくなったのは、なぜなのか、気になったのだ。
おそらく、キリスト教的な考えは、非信徒にも少なからず、波及しているのだろう。ま、そもそも、キリスト教的な、無から有を生み出せるという考えが、一体どういうものなのかもわかっていない。してみると、ある意味で私の本日のこのブログを書くという試みは、無から有を生み出す行為なのでは、いや、単に、前提材料について無知であるにもかかわらず、論理的風な展開を試みているだけの、まったくの無価値、より正確に言えば、害を及ぼすリスクさえある失敗作と言えるのかもしれない。